ハイブリッド開催でのユーザーストーリーマッピングワークショップ(JaSST'23 Tohokuワークショップ作成/運営話)
はじめに
2023/5/26(金)にJaSST'23 Tohokuがオンサイト(仙台市戦災復興記念館)/オンラインのハイブリッド開催されました。
この会のワーク担当として活動していたので、ワークショップの作成/運用話をまとめます。
同じようなワークショップをやりたい人の参考になれば幸いです。
ワークショップ概要
テーマ
JaSST'23 Tohokuのテーマは「アジャイルとテストと私たち ~明日『アジャイル』と言われたときに困らないためのヒント~」であり、アジャイル開発の普及により重要性が高まっているアジャイルテストを扱いました。
川口さんによる「アジャイルテスター視点で、ユーザーストーリーマッピングを活用した効果的なプロダクト開発」の基調講演*1からはじまり、長田さん、大平さん、半谷さん中村さんのそれぞれの実践的なアジャイルテスティングの事例紹介、スポンサー各社のLTなどボリュームのある構成となりました。
また、参加者に手を動かしてもらうために、実行委員コンテンツとして「ユーザーストーリーマッピング」を扱ったワークショップを実施しました。
テストを直接扱うワークではありませんでしたが、アジリティ(機敏性)の高いテストを行う上でテスト重要性の判断基準となる「ユーザー視点」を学ぶことは役に立つ、と考えてユーザーストーリーマッピングを選定しています。
この記事は、そのワークショップを主題として扱います。
ワーク内容
ワークは以下の2段構成になっています。3-5人程度のチームを組んで実施いただきました。
- 「朝起きてから家をでるまで」を考えよう
- 「乗換案内システム」で顧客への価値を考えよう
「朝起きてから家をでるまで」を考えよう
参加者が朝起きてから家をでるまで*2を付箋に書き出していただき、チームで共有いただきます。その後、「寝坊して5分で家を出なければならない場合に何をやるか」を検討いただきました。アジャイル開発を行う上で重要なMVP*3の考えを実感していただくことが目的となります。
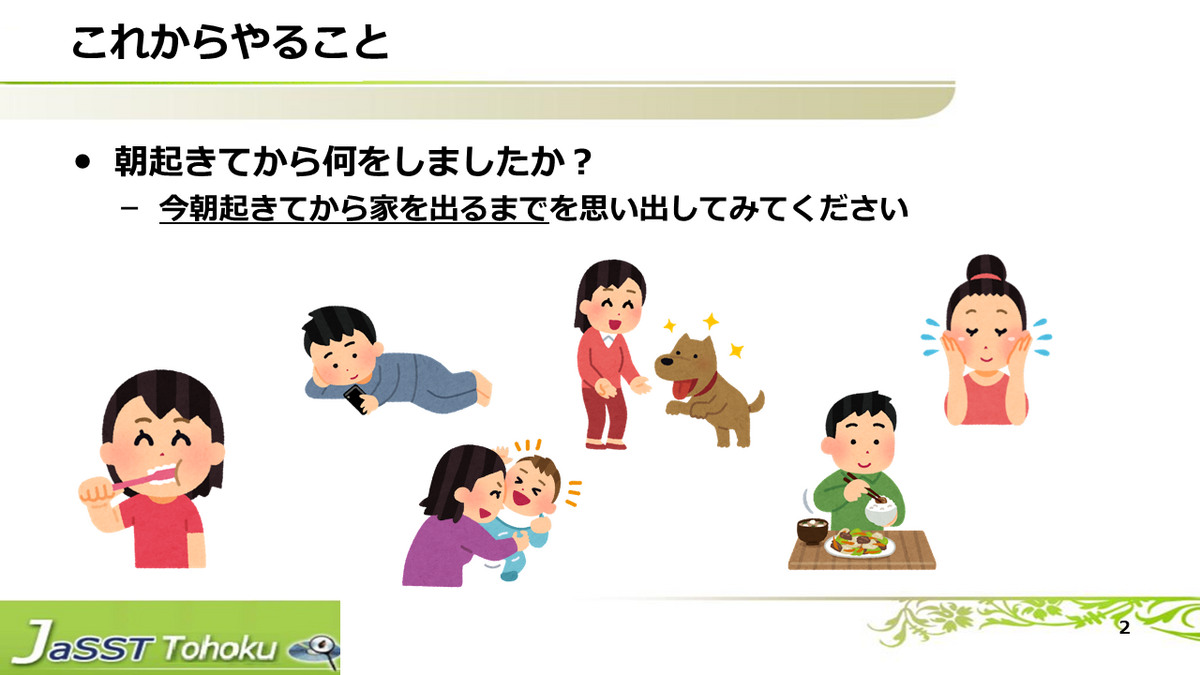
「乗換案内システム」で顧客への価値を考えよう
「乗換案内システム」を開発するために、ストーリーカード*4をもとにリリースに必要な機能を選定してもらいました。ストーリーカードや機能カードはあらかじめ用意されたものを使い、2回分リリースを疑似体験してもらうワークを実施いただきました。ユーザー視点を意識してMVPを考える感覚を体験いただくことが目的となります。

工夫したこと
JaSST'23 Tohokuはハイブリッド開催のため、ユーザーを以下の3属性に分けてワークショップを作成しました。それぞれの属性についての工夫をまとめます。
- オンサイト参加者
- オンラインワーク参加者
- オンラインワーク非参加者(視聴者)
オンサイト参加者
オンサイト参加者には一般参加者全員にご参加いただきました。ワークショップが本会の後半であり疲れていたと思いますが、みなさん積極的に取り組んでいただき有難い限りです。

一般的なペンと付箋のほか、時系列を表す線を引くためのロールタイプの付箋、機能カードやストーリーカードを印刷したもの*5を用意しています。
会場には多くの実行委員がいて参加者とのコミュニケーションも取りやすいため、今回の中では一番トラブルには対処しやすい運営スタイルでした。
オンラインワーク参加者
オンライン参加者にはMiroとDiscordボイスチャットでワークを実施いただきました。ワークへの参加は昼休み明けまでに参加者を募り、実行委員で3-5人のチーム分けを行いました。チーム用のワークスペースはあらかじめMiro+Discordに作成しており、割り振ったチーム番号のワークスペースに移動してもらうようにしています。

Miroでは以下の画像のようなワークスペースをチーム分用意しました。また、参加者はチームごとにDiscordのボイスチャンネルに入っていただき、チーム同士の会話を実施いただきました。ZoomのWebinarではブレイクアウトルームが使えないため、Discordのボイスチャンネルで個別ワークを実施いただくように対応しています。


また、オンラインでは人数がかなり多くなることが想定されていました*6。そのため、ワーク初めの説明では、オンライン参加者向けの説明を厚めに実施しています。説明を含む資料はワーク実施前に参加者に展開して、資料を見ながらワークができるようにしました。また、ワーク実施中はZoomから抜けてワーク実施後にZoomに戻ってもらうことがあるため、できる限りワークタスクのまとまりを大きくして切り替えが少なくなるようにしています。


オンラインワーク非参加者(視聴者)
オンライン参加者の中には、ワーク時間をすべて参加できない方*7がどうしても出てきます。特にJaSST東北のワークショップは1日のうちの一部でしかないので、ワークショップに参加できない方にも学べる内容を用意する必要がありました。
そのため、JaSST'23 Tohokuでは、オンラインのワーク実施風景を、実施者の音声込みでWebinarに配信させていただきました。対象となるチームは、あらかじめオンライン参加者の数名にお声がけして許可を頂いています。
運営配信側では、大きく以下の2つを実施しています。視聴者でもワーク参加者と同じ状況を共有できるので、ワークを疑似体験して学びが深くなることを期待しています。
- Miroの画面を配信に共有する。Miroの機能で、ワーク参加者の1名のマウスカーソルの動きを追従することができます。ワーク参加者の実際の動きを視聴者が追体験することができます。
- Discordのボイスチャンネルに入り、音声を配信に共有する。Zoomの画面共有時に「サウンドの共有」にチェックを入れることで、Discordボイスチャンネルでのワーク参加者同士の会話をZoomに共有することができます。運営PC上で鳴った音声は全て配信に載ってしまうため、Zoomの通知などを事前に切っておくなどの準備が必要です。

JaSST'21 Tohokuでも、今回のようにワーク参加者の実施状況を配信しました。その経験を活かした工夫です。
もっと工夫すべきだったこと
「オンラインワーク非参加者(視聴者)」向けにZoom Webinar上でワーク実施風景を共有しています。そのため、「オンラインワーク参加者」からワーク実施中にWebinarを切断しなければならず、ワーク実施後のWebinar再接続大変である旨の指摘をいただきました。
Zoom(Webinar)には現時点でスピーカーミュート*8機能が存在しません。そのため、オンラインワーク参加者はWebinarの音声を遮断するために、Zoomを切断する必要がありました。
例えば、Windows10にある「音声ミキサー」機能を使えば、アプリケーションレベルで音声操作を行うことができます。しかし、環境依存性があり、すべてのオンラインワーク参加者に実施いただくのは難しいため、Webinarの切断、再接続で対応いただくようお願いしています。

今後はツールの選定、調査などでオンラインワーク参加者の負担が減るように検討したいと思います。
おわりに
JaSST'23 Tohokuでは、いろいろな参加者の学びが深まるにはどうすれば良いかを考えて、準備をしてきました。
JaSST'23 Tohokuの参加者が「学んだ内容を活かしたい」と少しでも思っていただければ幸いです。
